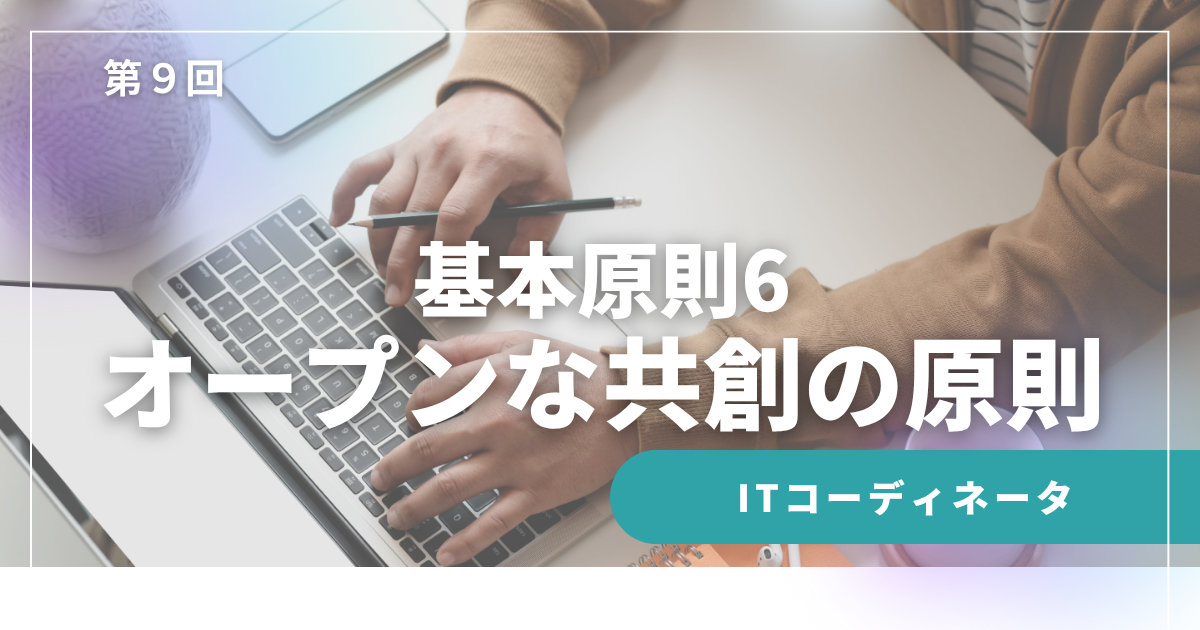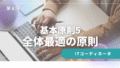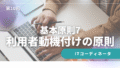ITコーディネータ協会の「ITコーディネータプロセスガイドライン Ver.4.0(PGL4.0)」は、デジタル社会で企業がその存在価値を高めていくための「実行基準(プロセス)」と「判断基準(基本原則)」を提供しています。PGL4.0では、これまでの7つの原則から「10の基本原則」へと再編されており、今回はその中から「基本原則6:自前主義から共創へ(オープンな共創の原則)」について解説します。
基本原則の定義と背景
「自前主義から共創へ(オープンな共創の原則)」は、「外部との共創も行えるオープンで自由な共創風土をつくる」ことと定義されています(PGL4.0 26ページ)。
この原則の背景には、「自社では気付けない新たな価値の発見とその実現には、外部との共創が必須となりつつある」という認識があります。企業が新たな価値を創造し、激しい環境変化に対応するためには、自社のリソースや知識に限定せず、外部の知見や能力を積極的に取り入れ、共に価値を創造する「共創」が不可欠であるという考えが根底にあります。そのためには、「外部との対話に躊躇しないオープンマインドと、他社とは違う明確な強みを持つ必要がある」とされています(26ページ)。
PGL3.1からの進化
旧版の「IT経営推進プロセスガイドライン Ver.3.1」にも、「オープンマインド醸成の原則」として「組織を超えて共創する」という考え方は存在しました。しかし、PGL4.0ではこの概念をより強調し、「自前主義から共創へ」という形で独立した基本原則の一つとして位置づけています 。これは、デジタル社会において外部との連携が単なる望ましい姿勢ではなく、新たな価値創出と事業変革のために「必須」となっている現状を反映した進化と言えるでしょう 。PGL4.0の改訂では、この原則が新たな要素として加えられたことも注意すべき点です。
デジタル時代における「共創」の深化
デジタル技術の進化は、企業間の連携のあり方を大きく変え、新たな「価値の連鎖(バリューチェーン)」を創造する可能性を広げています(前回記事「全体最適の原則」参照)。IoTや生成AIといった技術の利活用は、単一企業内で完結するものではなく、異業種を含めた「合従連衡」が必須となっています。
この原則は、企業がデジタル経営を推進する上で、以下のような視点を持つことの重要性を示唆しています。
- エコシステム思考:
自社だけでなく、顧客、パートナー、ITベンダー、さらには異業種企業といった多様なステークホルダーとの連携を前提に、ビジネスモデルを構築・変革する。 - オープンイノベーションの活用:
自社にないアイデアや技術を外部から積極的に取り入れる「オープンイノベーション」を推進し、アイデアソンやハッカソンといった手法を活用して変革の可能性を発見する(変革認識アクティビティP1、34ページ上部) - 心理的安全性の高い環境作り:
社内外問わず、意見交換や失敗を恐れない心理的に安全な環境が、真の共創を促します(基本原則9「学習と成長の法則」も参照)。
ITコーディネータの実践
ITコーディネータは、企業が「自前主義」から脱却し、「共創」の文化を根付かせるための重要な役割を担います。
- 共創の機会特定と推進:
顧客企業のビジネスモデルや課題を深く理解し、外部パートナーやテクノロジーとの共創によって新たな価値が生まれる機会を特定します。その上で、共創プロジェクトの立案と推進を支援します。 - オープンマインドの醸成支援:
企業文化として「自前主義」が根付いている場合、外部との連携に対する抵抗が生じることがあります。ITコーディネータは、経営者や従業員に対し、共創のメリットを伝え、オープンな対話と協力の姿勢を促すことで、組織全体のオープンマインド醸成を支援します。 - パートナー選定と関係構築:
適切な外部パートナーを選定し、信頼関係を構築するためのプロセスを支援します。これには、調達要件の明確化や、公平で透明性のある選定プロセスの確立などが含まれます(デジタル経営実行計画プロセスP3のタスク7「IT資源調達計画」、69ページ)。 - 価値の最大化とリスク管理:
共創によって生み出される価値を最大化しつつ、外部連携に伴うリスク(セキュリティ、知的財産等)を適切に管理するための助言や仕組みづくりを行います (共通基盤CB-4「セキュリティ」、113ページ)。
「自前主義から共創へ(オープンな共創の原則)」は、企業が孤立することなく、外部との連携を通じて持続的な成長と新たな価値創造を実現するための、デジタル経営における重要な判断基準の一つです。
次回は、「基本原則7:利用者との関係をより深める(利用者動機付けの原則)」について解説します。
PGL4.0で新しく整理された「デジタル経営を成功に導く10の基本原則」全体概要はこちら。