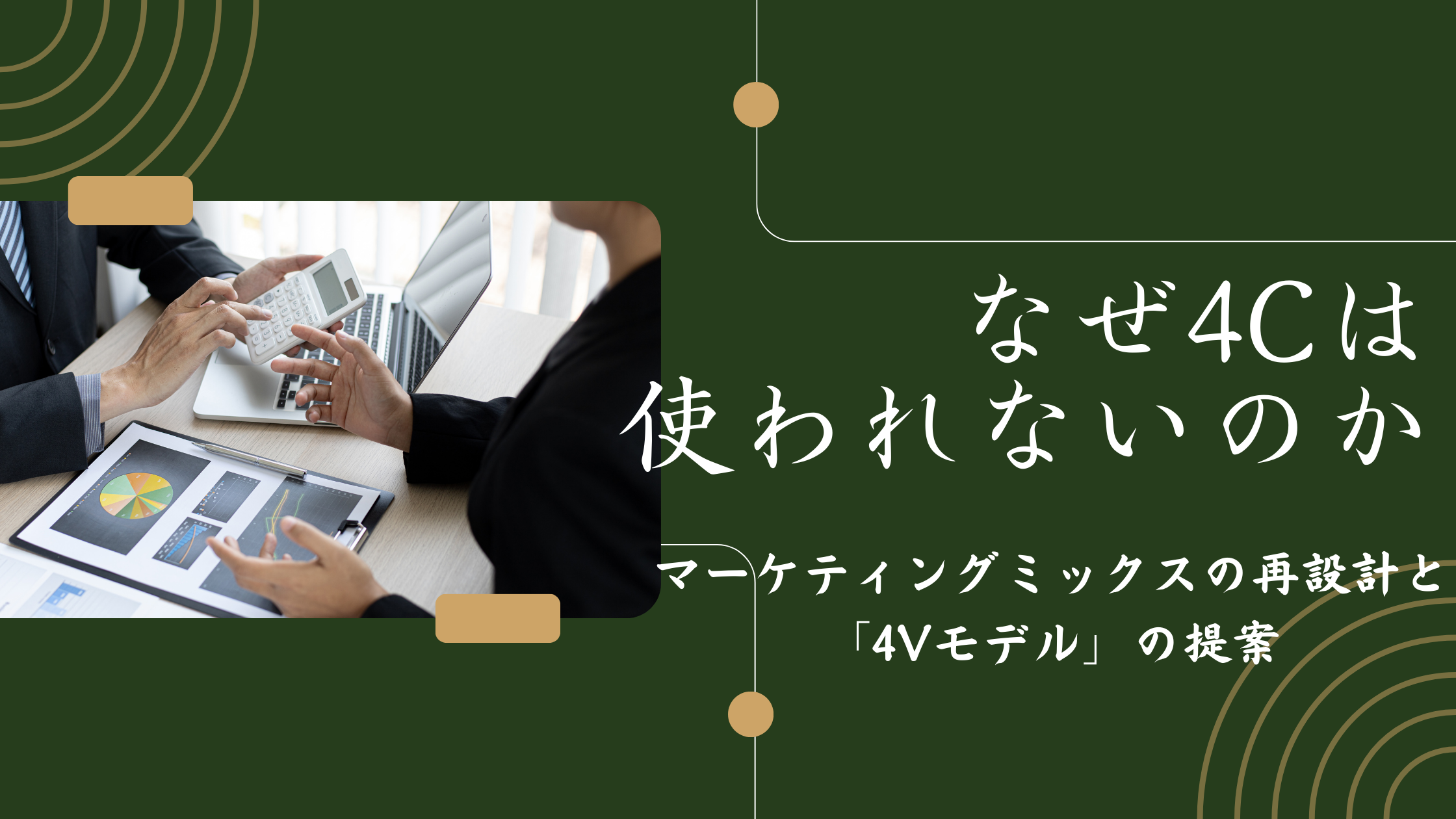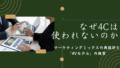前回の記事では、マーケティング・フレームワークとして4Pと並び称される4Cが、なぜ実務の中で十分に定着してこなかったのか──その構造的な理由について検証を試みました。
今回はその考察を踏まえ、4Cの理念を引き継ぎながらも、より実務に適したかたちで再構築した新しい視点「4Vモデル」を提案します。
4Pと4Vを補完的に活用することで、顧客体験を起点としたマーケティング戦略がどのように設計・検証できるのか、その実効性について考察していきます。
新提案:「4Vモデル」──顧客体験の4つの価値軸
そこで、4Cの問題点を踏まえたうえで、より実務に耐えうる形として「4Vモデル」を提案します。
| 項目 | 概要 | 参考対応(4P、4C) |
|---|---|---|
| Value(価値) | 顧客が得る主観的な価値(感情・象徴含む) | Product / Customer Value |
| Viability (妥当性) | 顧客が「見合っている」と感じる負担と納得感 | Price / Cost |
| Venue (体験の場) | 接点における心地よさ・違和感のなさ | Place / Convenience |
| Voice (共感) | 共鳴・つながり・対話を感じる関係性 | Promotion / Communication |
各要素の意味
- Value(価値):機能的・情緒的・社会的価値など、顧客が本当に求めているもの
- Viability(妥当性):金額に限らず、時間・手間・精神的負担を含めた総合的な「妥当性」
- Venue(体験の場):店舗、Web、アプリなど、接点における体験の心地よさやスムーズさ
- Voice(共感):顧客が「このブランドは自分をわかってくれる」と感じられるつながり
4P/4C/4Vの対応表
これら4Vについて、大先輩である4Pや4Cとどう対応するかについて、その視点の変換も含めてまとめると以下のようになります。
| 4P(企業) | 4C(顧客) | 4V(顧客体験) | 視点の変換 |
|---|---|---|---|
| Product | Customer Value | Value(価値) | 機能から意味・感情へ |
| Price | Cost | Viability (妥当性) | 金額から納得感へ |
| Place | Convenience | Venue(体験の場) | 利便性から心地よさへ |
| Promotion | Communication | Voice (共感) | 発信から共鳴へ |
活用例:クラシック音楽のコンサートではどうなる?
適用例として、あるクラシックオーケストラを想定して、このオーケストラのマーケティング施策を4Vで説明できるかどうかについて検証してみます。
| 4V | 顧客が感じることの例 |
|---|---|
| Value (価値) | 演奏による癒し、非日常、感動、推し奏者への共感、満足感 |
| Viability (妥当性) | 〇〇円のチケットでも「それ以上の価値を得た」あるいは「妥当だった」と思える |
| Venue (体験の場) | 会場の快適さ、チケット購入のしやすさ、会場までの経路、スタッフの案内などの体験 |
| Voice (共感) | SNSでのつながり、舞台裏のエピソード、共感できるメッセージ、口コミなど |
このように切り分けると、いわゆる「カスタマージャーニー(顧客の購買行動プロセス)」との親和性も高く、使いやすいフレームワークになっているのではないかと思います。
検証:4Cと比べてどうか?
ところで、4Cのところで、特にPromotionの社内向け施策がカバーできていないと指摘しましたが、これは4Vでもカバーしていません。この点も含めて、4Cと比べてどう改善したのかを以下にまとめました。
| 4Cでの欠点 | 4Vでの克服度 | 補足 |
| 抽象性が高く実務に合わせづらい | ◎:4Vでは各項目が施策に直結しやすいよう具体化されている | 4Cの抽象性を構造化・再定義して施策への展開力が向上した |
| MECEでない | ◎:主観軸で整理し直し、被りも役割で差別化。実務で使える単位になっている | Value⇔Viabilityは、価値とそれに見合う負担感の評価に整理され、トレードオフではなくなった VenueとVoiceにはSNS体験など若干の重なりはあるが、タッチポイントvs感情共鳴という定義で棲み分けできる |
| 命名に統一感がない | ◎:全て1語で覚えやすい設計 | 互いの排他性も確保 |
| 略称が3Cと混同される | ◎:C→Vに変更して回避できている | マーケティングの領域では、Vを使った3Cほど有名なフレームワークはない(3Vというのは存在しますが、知名度で3Cには及ばない) |
| 内部向け施策がPromotion相当のアイテムに含まれない | ×:4Vでも4Cと同じく、内部施策についてはカバーしていない | 4Cも4Vも、顧客視点である関係上、社内施策は含められない |
以上、総合的に見て、4Cの4つの構造的欠点に対しては、4Vモデルは実務的かつ戦略的に、ほぼすべてを補完・改善していると言えます。
一方で、たとえばPromotionにおける営業インセンティブなどの社内施策のように、4Vではカバーしきれない領域も存在します。
そのため実務においては、4P(企業視点の施策設計)と4V(顧客体験の視点)を併用し、「内から外、外から内」を照らし合わせるように戦略を検証・補完するアプローチが効果的です。
言い換えれば、4Pが「施策を描く地図」だとすれば、4Vは「それが顧客にどう映っているかを見る鏡」として、具体的に検証できるツールとして使うことができます。
このように4Vは、4Cをより具体化・構造化した上で、実務でも活用できるフレームへと再定義したモデルと位置付けることができます。
おわりに:顧客視点は再構築できる
4Cは「顧客の立場に立とう」という思想としては有用でしたが、実務の中では構造的に扱いづらい側面がありました。
今回ご提案する「4Vモデル」は、顧客体験をより具体的に捉えながら、4Pや4Cとも接続可能な構造を備えた「顧客体験フレームワーク」と言えるのではないか、と自負しています。
今後のマーケティング戦略やサービス設計の中で、ご活用いただければ幸いです。
ご興味をお持ちいただけた方へ
この考え方に関心をお持ちいただけた方のために、今後の展開をお知らせします。
- 図解資料をご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
- 今後、ワークショップ用テンプレートも順次公開予定です。
💡用語の補足
- カスタマージャーニー:顧客が商品やサービスに出会い、興味を持ち、購入・利用し、ファンになるまでの一連のプロセスを旅路になぞらえて可視化したもののことです。
- SNSや広告で「知る」段階から、比較・検討し「買う」、そして「使った後どう感じるか」までを含みます。
- 企業はこの流れを分析することで、どこで顧客が離れるか、何に満足しているかを把握できます。
- 購買行動だけでなく、感情や体験も重視するのが特徴です。
- マーケティング戦略やサービス改善の土台として、非常に重要な考え方です。
- タッチポイント:企業と顧客との接点のことです。段階に応じた複数のポイントがあります。ブランドイメージを高め、購入の動機や顧客のファン化を促進するきっかけになります。
- 購入前:広告(Web、マスメディア、紙)、ブログ、口コミサイトなど
- 購入時:店舗、販売スタッフ、通販サイト・EC、パッケージや包装など
- 購入後:アフターサービス、ユーザーコミュニティなど
- 感情共鳴:楽しんでいる人の隣にいると、自分も楽しくなってくるような、いわば「共鳴」するような現象をいいます。例えば、SNSでよい口コミをたくさん見れば、自分も同じ体験をしたい、と考えるようになります。