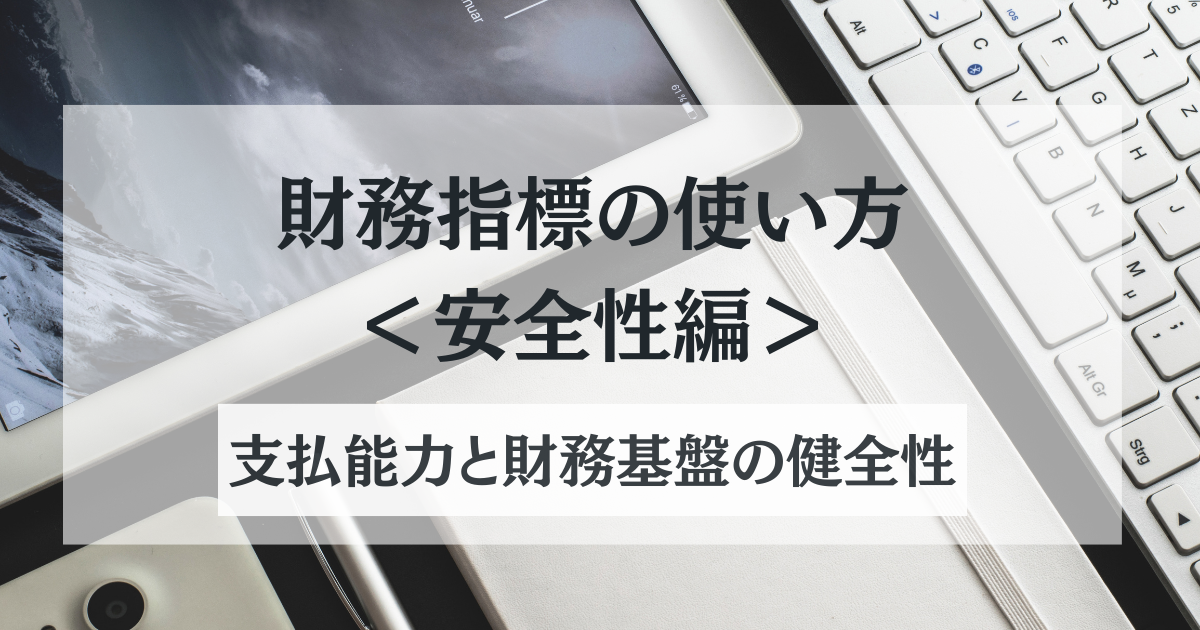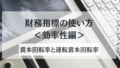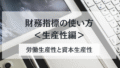お客様企業の財務諸表を分析するとき、安全性の指標は「支払能力」や「財務の安定性」を確認するうえで欠かせません。
短期的に資金繰りが持つか、長期的に財務基盤が安定しているかを、数値で把握することができます。
本記事では、安全性を測る代表的な8つの指標を 4つの観点 に整理して解説します。
短期安全性
流動比率
$$
流動比率=\frac{流動資産}{流動負債} \times 100 \; (%)
$$
・定義:流動資産(1年以内に現金化できる資産)が流動負債(1年以内に返済する負債)に対してどれだけあるかを示す。
・見方:
- 高い場合(200%前後が理想、100%以上なら許容範囲) → 短期的な支払能力が十分。
- 低い場合(100%未満) → 短期資金繰りに不安がある可能性。
・実務ポイント:
- 売掛金や在庫の健全性
- 短期借入金の返済スケジュール
- 資金繰りの余裕度
➡ 「短期的な支払能力」を測る基本指標。
当座比率
$$
当座比率=\frac{当座資産}{流動負債} \times 100 \; (%)
$$
(当座資産=流動資産 − 棚卸資産 − 前払費用 など)
・定義:すぐに現金化できる資産(現金・預金・売掛金など)が流動負債に対してどれだけあるかを示す。…棚卸資産などは、いざ資金ショートしそう!というときに、実はすぐ換金できるかどうかは怪しいので、除いておくということですね。(売掛金だってそうですが、あくまで比較の観点で)
・見方:
- 高い場合(100%以上が理想、70%くらいまでが許容範囲) → 短期的な支払余力が十分。
- 低い場合(70%未満) → 在庫依存が高く、緊急時に資金繰りが難しい。
・実務ポイント:
- 売掛金の回収スピード
- 現預金の残高
- 在庫依存度の高さ
➡ 「より厳格に短期的な支払能力」を見る指標。
長期安全性
固定比率
$$
固定比率=\frac{固定資産}{自己資本} \times 100 \; (%)
$$
・定義:固定資産を自己資本でどれだけ賄えているかを示す。
・見方:
- 100%以下が理想 → 固定資産を自己資本でまかなえている。
- 高い場合 → 借入依存で固定資産を保有している可能性。
・実務ポイント:
- 設備投資と資本調達のバランス
- 借入依存度の把握
- 長期安定性の確保
➡ 「自己資本で固定資産を保有できているか」を見る指標。
固定長期適合率
$$
固定長期適合率=\frac{固定資産}{自己資本+固定負債} \times 100 \; (%)
$$
・定義:固定資産が自己資本と長期負債でどの程度まかなえているかを示す。
・見方:
- 100%以下が理想 → 長期安定資金で固定資産を保有。
- 高い場合 → 短期資金で固定資産を賄っているためリスク。
・実務ポイント:
- 長期借入金の返済条件
- 自己資本比率との組み合わせで判断
- 業種ごとの適正水準を参照
➡ 「固定資産を長期安定資金で持てているか」を測る指標。
💡ところで、この「固定長期適合率」という言葉は理解するのに厄介な構造を取っている言葉です。定義は上に書いた通り、固定資産を自己資本+長期負債でどの程度まかなえているか?というものですが、教科書には軒並み「この値は低い方がいいのです」と書いてあるのです。
しかし、適合率というのなら(カバーできている程度なのだから)、その値は高い方がいいのでは?と考えるのが自然ですが、そうはなっていません。この混乱を避けるには、この指標は安全性を「2段階で測るものだ」と考えるとよいでしょう。つまり、
1.最初の判定:固定長期適合率が100%以下か?
・Yesの場合:固定資産が長期資金でまかなえているので適合している。
・Noの場合:固定資産の一部が短期資金でまかなわれているので不適合である(危険!)。
2.引き続いての判定:100%以下で(=適合している)場合、その値はどれくらいか?
・例1:90%くらい:適合しているが、ギリギリ
・例2:70%くらい:より健全
・例3:50%くらい:長期資金にかなり余裕がある
というように、まず閾値評価として100%を超える(不適合)か超えない(適合)かを判定し、そのあとで定量評価としてその値が何%なのかを見て長期資金の余裕の度合いを見るものだ、と考える必要があります。ややこしいですね。
なお、この値が不適合な場合は、たいてい借入金(しかも、短期返済が必要な)がかさんでいるわけなので、上で説明した流動比率・当座比率や、下で説明する資本調達構造の安全性指標が悪化します。
返済余力
インタレスト・カバレッジ・レシオ
$$
インタレスト・カバレッジ・レシオ=\frac{営業利益+受取利息・配当金}{支払利息}
$$
・定義:営業利益などで利息をどの程度カバーできているかを示す。
・見方:
- 3倍以上が理想 → 利払い能力に余裕。
- 1倍未満 → 営業利益で利息すらまかなえない状態。
・実務ポイント:
- 借入金の利息負担の大きさ
- 金利上昇局面での耐性
- 金融機関が融資審査で重視する指標
➡ 「利息支払能力」を測る代表的な指標。
債務償還年数
$$
債務償還年数=\frac{有利子負債-現金預金}{税引後利益+減価償却費}
$$
・定義:返済原資(税引後利益+減価償却費)で有利子負債を返済すると何年かかるかを示す。
・見方:
- 短い場合(5〜7年以内が目安) → 借入金返済能力が高い。
- 長い場合 → 資金繰りにリスク。
・実務ポイント:
- 長期借入金の返済計画の健全性
- 減価償却費の大きさと資金創出力
- 金融機関が融資姿勢を決める際の参考値
➡ 「借入金を返済するのに必要な年数」を直感的に示す指標。
資本調達構造の安全性
自己資本比率
$$
自己資本比率=\frac{自己資本}{総資産} \times 100 \; (%)
$$
・定義:総資産に占める自己資本の割合。
・見方:
- 高い場合(30%以上が目安) → 財務基盤が安定。
- 低い場合 → 借入依存度が高い。
・実務ポイント:
- 株主資本の厚み
- 借入依存度の確認
- 業種平均との比較
➡ 「財務体質の健全性」を測る代表的な指標。
負債比率
$$
負債比率=\frac{負債}{自己資本} \times 100 \; (%)
$$
・定義:自己資本に対する負債の割合。
・見方:
- 高い場合 → 借入依存が大きくリスク高。
- 低い場合 → 自己資本中心で安定。
・実務ポイント:
- 借入金返済負担の大きさ
- 自己資本とのバランス
- 金融機関が注目する財務指標
➡ 「負債依存度と財務リスク」を測る指標。
💡短期であれ長期であれ負債が大きいと、自己資本比率は下がり、負債比率は上がります。どちらも負債の状況を反映するので、負債の評価に使えると言えるのですが、この二つの指標は目的が違うので使いわけが必要です。つまり、
・自己資本比率:企業がどれだけ自己資本で運営されているか(安定性)
→財務の健全性を評価したいとき
自己資本比率が高いほど、倒産リスクが低く、信用力が高い※
・負債比率:自己資本に対してどれだけ負債に依存しているか(リスク)
→資金調達のレバレッジを見たいとき
負債比率が高いほど、レバレッジ効果はあるがリスクも高い
ということが言えるため、銀行・経営者・株主・M&A先等々見る人によって使う指標が異なってきます。
※一般的に「自己資本比率は高いほど良い」とされますが、この評価を中小企業・小規模企業にそのまま当てはめると、実態を見誤る可能性があります。 自己資本の厚い企業は、裏を返せば借入による資金調達(レバレッジ)をあまり活用しておらず、成長投資や事業拡大へのチャレンジが抑制されている可能性もあります。 この指標は、主に中堅以上の企業における財務安定性の目安として語られるものであり、企業規模や成長フェーズに応じた柔軟な評価が必要です。 (なお、大企業向けの企業研修などでは、こうした視点はあまり強調されない傾向があります)
まとめ
安全性の指標は、短期と長期、さらに返済能力と資本構造まで含めて総合的に確認することが重要です。
- 短期安全性:流動比率、当座比率
- 長期安全性:固定比率、固定長期適合率
- 返済余力:インタレスト・カバレッジ・レシオ、債務償還年数
- 資本調達構造の安全性:自己資本比率、負債比率
これらを組み合わせて分析することで、お客様企業の資金繰りと財務基盤の安定性を多角的に把握できます。