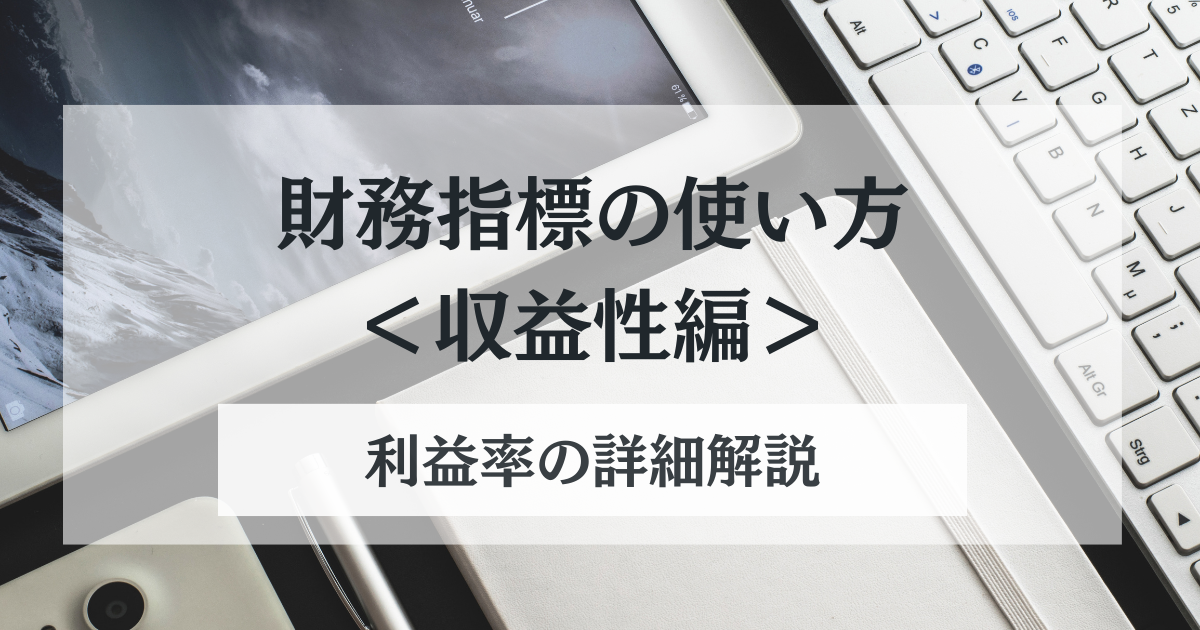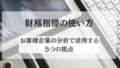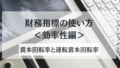お客様企業の財務諸表を分析するとき、最初に確認すべき指標のひとつが「収益性」です。
収益性は 「売上に対してどれだけ利益を残しているか」 という狭義の意味と、「資産や資本をどれだけ効率的に活用しているか」 という広義の意味に分けられます。
本記事では、収益性を評価する財務指標のうち、狭義のもの(売上高○○利益率)について解説します。
広義の収益性、すなわち総合収益性を表す指標(ROA、ROE)については、別記事にて解説していますので、そちらも併せてご参照ください。
狭義の収益性(利益率分析)
売上高総利益率(粗利率)
$$
売上高総利益率=\frac{売上総利益}{売上高} \times 100 (%)
$$
(ただし、売上総利益 = 売上高 − 売上原価)
- 定義:売上高に対してどれだけ粗利益(売上高−売上原価)を確保できているかを示す。
- 見方:この指標が低い場合、仕入れ値や製造コスト(つまり原価)が高止まりしている可能性がある。そのほかには、不良在庫や廃棄ロス、価格競争の激化が疑われる(いずれも原価率が悪化するため)。
逆に高い場合は、差別化商品やブランド力で価格転嫁ができている状態といえる(つまり、利幅がちゃんと取れている)。
この指標を一言でいうと、「価格戦略や原価管理の成果を図る指標」と言えます。 - 実務ポイント:
- 仕入先との価格交渉力
- 在庫ロスや廃棄ロスの管理体制
- 商品ラインナップの付加価値の有無
➡ 「価格転嫁できているか」「差別化商品で利益を稼げているか」の確認に有効。
売上高総利益率(粗利率)を通じて原価について分析し、特に問題がないようであれば、次の「売上高営業利益率」で販管費などのチェックをしていきます。
売上高営業利益率
$$
売上高営業利益率=\frac{営業利益}{売上高} \times 100 \; (%)
$$
(ただし、営業利益 = 売上総利益 − 販売費及び一般管理費)
- 定義:本業の収益力を測る指標。営業利益 ÷ 売上高。
- 見方:この指標が低い場合は販管費や人件費など固定費の負担が重い。そのため、売り上げを増加しても利益になかなか繋がらないことになる。
高い場合は、コスト構造が効率的で、事業基盤が強い。
この指標を一言でいうと、「事業運営の効率性や固定費構造の健全性を把握する指標」と言えます。 - 実務ポイント:
- 販促費・広告費の投資対効果
- 人件費や外注費の比率
- 店舗運営や拠点配置の効率性
➡ 「売上が伸びても利益が増えない」場合、この指標をチェック。収益構造の改善余地を見極める。
販管費などにも問題がなければ、次に「売上高経常利益率」に移り、例えば借入が嵩んで利息の支払いが苦しくなっていないか?などという観点でチェックをしていきます。
売上高経常利益率
$$
売上高経常利益率=\frac{経常利益}{売上高} \times 100 \; (%)
$$
(ただし、経常利益 = 営業利益 + 営業外収益 − 営業外費用)
- 定義:経常利益 ÷ 売上高。本業に金融収支を加えた収益力を示す。
- 見方:営業利益率に比べて大きく下がっている場合は、借入金の利息負担が重い可能性がある。
この指標を一言でいうと、「財務戦略(資金調達)の健全性を判断する指標」と言えます。営業と財務のバランスを見極めることができます。 - 実務ポイント:
- 借入金依存度と利息負担の妥当性
- 為替差損益などの財務収支の安定性
➡ 「本業では黒字だが金融費用で赤字」になっていないかを把握。財務戦略の検討材料になる。
設備投資をするために長期借入金をしたので、利息がドカンとのしかかってきました、というようなときにこの値が悪化します。貸借対照表を見て、有形無形の固定資産が増えていたら、それを購入するために借りたお金(負債)と併せてチェックしてみましょう。
ここの指標でも問題がなければ、最終的に次の「売上高当期純利益率」を見るのですが、この指標はいわゆる特損といったイレギュラーが響く指標なので、定常的な会社の営みによる影響ではないということになります。どちらかというと株主や投資家向けの分析になっていきます。
売上高当期純利益率
$$
売上高当期純利益率=\frac{当期純利益}{売上高} \times 100 \; (%)
$$
(ただし、当期純利益 = 経常利益 ± 特別損益 − 法人税等)
- 定義:当期純利益 ÷ 売上高。最終的に企業に残る利益の割合。
- 見方:法人税や特別損失の影響を受けやすい。短期的なブレが大きい。
この指標は、一時的な要因か、構造的な問題かを切り分けることが必須になります。
一言で言うと、「株主還元や内部留保に直結する最終的な収益力を示す指標」と言えます。 - 実務ポイント:
- 税負担率の確認(節税余地があるか)
- 特別損益(固定資産売却損・投資損失)の一時的影響を分離
- 株主還元や内部留保に回せる利益規模の把握
➡ 「本当に会社に残る利益」を見極める。経営者や投資家への説明資料に直結。
まとめ(狭義の収益性)
利益率の分析は、
- 粗利益率:商品・サービスの付加価値
- 営業利益率:本業の収益力
- 経常利益率:財務活動を含めた全体の収益力(ここまでがレギュラーな活動の影響)
- 当期純利益率:最終的な利益確保力(イレギュラーも含めた、いわゆる泣いても笑っても「戦いの結果」である)
という階層的な理解が重要です。
数字の高低を見るだけでなく、なぜそうなっているのか、どの費用構造が影響しているのか まで掘り下げることで、具体的な改善施策につながります。言い方を変えると、「どの段階で利益が削られているかを把握する」ことで、改善ポイントを明確にする出発点となります。