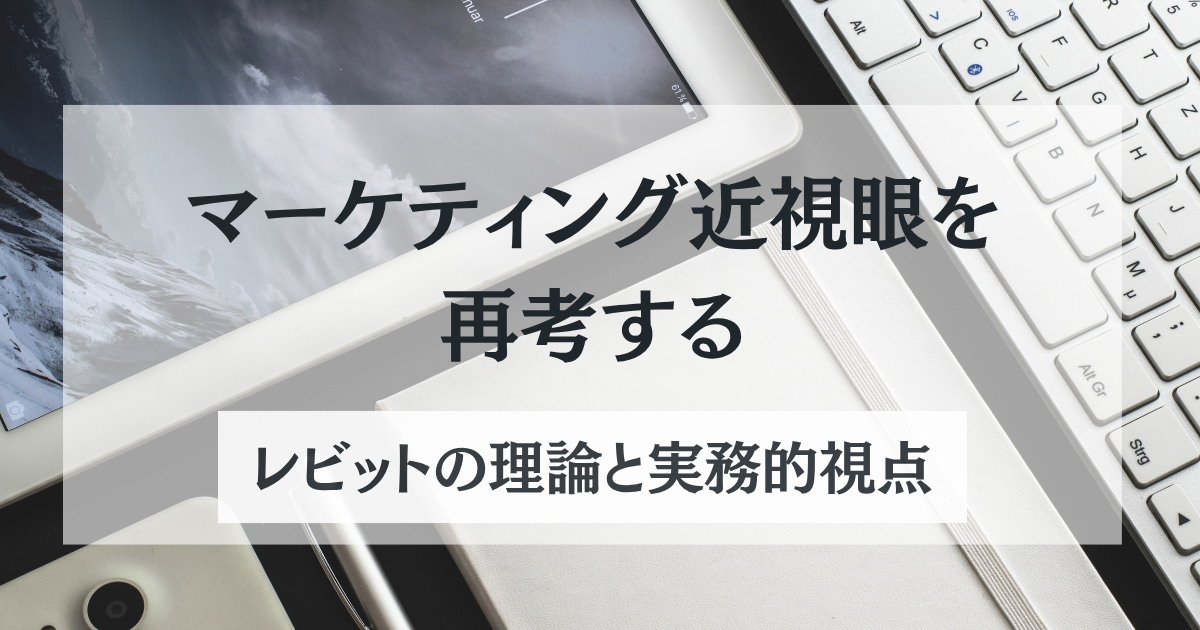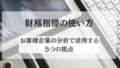マーケティングの古典的名著『マーケティング近視眼(Marketing Myopia)』を、研修やビジネススクールで学ばれた方も多いでしょう。私自身も新人研修で初めて聞いた時、目から鱗が落ちるような衝撃を受け、以来約30年、この理論を尊敬しつつも、ある種の「引っ掛かり」を感じ続けてきました。今回はその「引っ掛かり」を掘り下げながら、『マーケティング近視眼』の現代的な解釈を考えてみます。
マーケティング近視眼とは
ハーバード・ビジネススクール教授のセオドア・レビットが1960年に発表した理論で、「企業は顧客が真に求めている価値に集中すべきであり、自分たちの提供する手段に(近視眼的に)囚われてはならない」と提言したものです。レビットは具体例として、「アメリカの鉄道会社は自らを『鉄道』と定義したために衰退した。『輸送業』として捉えれば衰退を免れた可能性がある」と指摘しています。
実務家の違和感:固定資産はどうする?
レビットの指摘は鋭く正しいと思いますが、実際に経営に携わると、「膨大な鉄道インフラ(固定資産)を持つ鉄道会社が簡単に輸送会社へ転換できるのか?」という疑問が生じます。鉄道という特定用途資産は航空や自動車に簡単に転換できません。
また、実際のビジネスでは「輸送業」というドメインさえも狭く感じられることがあります。輸送に限定せず、不動産開発や商業施設運営など、さらに広いドメインで成功を収めた日本の鉄道会社の事例を見ると、レビットの提案自体も実は限定的だったのでは、という疑問が浮かびます。
日本の鉄道会社の現実的な成功モデル
日本の鉄道会社(JR東日本、東急、阪急など)は、レビットの想定を超え、「輸送」だけでなく「地域生活インフラ」へと事業ドメインを広げました。駅ビル開発やホテル運営など、「人が集まる場所をつくる」ことに成功し、鉄道利用者が減少しても収益を確保しています。
JR東日本の『From AQUA(旧:大清水)』は、新幹線のトンネル工事中に出た湧水を商品化したもので、鉄道という固定資産に由来する副産物をビジネスに転換した好例です。このような具体例を見ると、「鉄道→輸送」という単純化された議論では捉えきれない現実が明らかになります。
鉄道のライバルは誰だったのか?
レビットが指摘したように、アメリカの鉄道会社の衰退要因にはライバルの台頭がありました。主なライバルとしては以下が挙げられます。
- 自動車業界:高速道路網の整備によるマイカー利用やトラック輸送の普及
- 航空業界:長距離旅客輸送の台頭
- 航空貨物業界(FedExなど):速達性、確実性、利便性を提供する新たな輸送価値を創出
特にFedExの成功は、後年の解説などでマーケティング近視眼の典型例として挙げられることが多いですが、レビット自身がFedExに直接言及していたわけではありません。ただ、FedExの成功は、鉄道業界が「自分たちとは無関係」と軽視した新たな輸送価値を生み出した典型例として知られています。
レビットの議論を補完する実務的視点
レビットの理論の本質は「顧客ニーズに目を向けよ」という普遍的な価値観を示しています。一方で、実務家としての経験を通して見えてくるのは、理論の限界とそれを現実の経営にどう補完すべきかという視点です。
- 固定資産や技術、人材などの現実的な制約を理解する。
- ドメインを単に広げるのではなく、現有資産を多面的に活用する。
- 顧客が本当に求めている価値を深掘りし、事業を再定義する。
教育の場では、このような実務的な補完視点を示すことで、理論と現実を橋渡しし、深い理解を促すことが可能になります。
結論:理論と実務の橋渡しをする重要性
レビットの『マーケティング近視眼』はマーケターのバイブルとして、これからも繰り返し受け入れられ再利用されるでしょう。しかし、さらにもう一段階、実務的な視点を加えることでその理解は深まります。理論を現実に応用する際には、単なる理論の追従ではなく、現場での実践的な再解釈が必要です。
今回の考察を通じて、理論と実務を結びつける重要性を改めて実感しました。今後、教育やビジネスの現場で『マーケティング近視眼』を教える際には、このような現実的な視点も添えて伝えることを提案します。
【コラム】教会という「集まる場所」
アメリカにおいて「人が集まる場所」として教会は特別な位置を占めています。教会は単に宗教的な活動の場だけでなく、地域コミュニティの中心的役割を担っています。鉄道が「人々が移動し集まる機会」を提供していたように、教会もまた、地域住民が定期的に集まり、交流を深める場を提供しています。
現代のマーケティング視点で見ると、「人が集まる」機能を持つ場所は、多面的に捉える必要があります。教会やコミュニティセンターなどが、間接的に鉄道を含む輸送業の価値に影響を与えている可能性もあり、これもまたレビットの理論を現代的に再解釈する一つのヒントとなるでしょう(ただ、一般的には教会には電車で向かうことは少ないようです。20年ほど前にアメリカで見た、新興住宅地の近くの丘にできた「巨大駐車場完備」の教会は印象的でした)。
さらに、2025年時点での同時代的な視点で見ると、人々がどこで、どのように集まるのか(オンラインを含めて)もまた、輸送業の提供する「移動」という価値に影響を与えている可能性があります。鉄道会社がこうした社会の変化を軽視すれば、結果として利用者が減り、間接的に影響を受けることもあり得ます。
実際に、近年の鉄道会社が豪華列車を続々と提供しているのは、「移動」ないしは「集まる」という体験そのものを、オンラインで代替できない独自の価値として訴求するためでもあるように見えます。