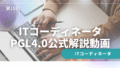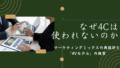──心に残る価値をどう届けるか
2025年、政府・与党によって検討されている「一律2万円給付」は、物価の上昇によって家計に負担がかかる今、間違いなく多くの人にとって助けになる支援策と言えます。報道によると、全国民に2万円を配布し、住民税非課税世帯や子育て世帯にはさらに2万円を上乗せすることで、最大4万円の支給が予定されています。
現金は、誰にとっても使い道が自由で、最もフレキシブルな支援のかたちといえるでしょう。しかし、一方で、こんなことを思ったのも確かです。
「もし、同じ2万円分を、“いま高騰しているお米”、例えば5kgのお米4袋、あるいは5袋で受け取ったとしたら、そっちのほうが嬉しいのではなかろうか」
「いや、現金の方がいいに決まってるでしょ」とか、賛否両論あるかとは思います。ただ私自身、以前「ハーゲンダッツ約3,000円分の引換券」をもらったとき、同じ額の現金をもらうより遥かに心が躍った経験があります。もちろん、現金があれば同じものを買えるわけですが、不思議なことに“引換券”というかたちで受け取ったほうが、喜びが鮮明に残ったのです。
同じ価値なのに、なぜ“嬉しさ”が違うのか?
このような感情の違いには、心理学や行動経済学の観点からいくつかの説明がされています。
心の中の「財布」は、一つではない
まず、「メンタルアカウンティング(心の会計)」という考え方があります。人はお金を、目的ごとに無意識に“財布を分けて”管理しているというものです。
現金であれば、どうしても「生活費」や「光熱費」あるいは「貯金」などに振り分けられ、合理的・効率的に消費されます。一方で、ハーゲンダッツの引換券や、たとえば「お米5kg×5袋」のような支援なら、日々の生活の中で「嬉しさ」や「ありがたみ」とともに繰り返し思い出される対象となり、記憶に定着しやすくなります。つまり、「ああ、これは自分のための贈り物だ」と感じやすく、感情に直接触れてくるのです。
「自由度」より「意味のある体験」が心に残る
現金は、便利な反面、選択肢が多すぎて“嬉しさ”がぼやけてしまうことがあります。実際、「何に使うか迷っているうちに、結局いつのまにか消えていた」という方も多いのではないでしょうか。あるいは、特に慎重な性格の方や、家計を切り詰めている家庭においては、せっかくの給付金も「もったいなくて使えない」という心理が働きやすくなります。
対して、目的がある程度決まっている贈り物には、「迷わなくて済む安心感」と、「手にしたときの具体的な喜び」がセットになっています。つまり、消費されるまでのプロセス全体がポジティブな体験として認識されやすくなります。
たとえば、重たいお米を運びながら「助かるなあ」と思う場面は、その後も生活の中で何度も記憶に残るかもしれません。
感情に届く“体験”は、贈り手の意図まで伝える
現金は形を持たず、手渡しでもされない限り、感覚的に「何かを受けとった」という実感が希薄になりがちです。一方、例えば「お米5kg × 5袋」をもらったとすれば、その重みや置き場所、食卓に並ぶ風景など、具体的な生活の中で繰り返しその存在を実感する機会があります。こうした視覚・触覚・味覚などを伴う”体験の価値”は、単にモノとしての価値を超えて、「思い出に残る」、あるいは「誰かの気持ちを感じる」といった情緒的な価値にもつながっていきます。
この“体験価値”の積み重ねが、人と人、あるいは人とブランド・組織との関係性をつくっていく。そんなこともあるのではないでしょうか。
ビジネスにも応用できる「嬉しさの設計」
今回の話は、政策設計に限らず、企業のマーケティングや顧客体験設計にも通じるものです。どれだけ優れたサービスであっても、ユーザーの心に残らなければ、継続的な関係性にはつながりません。私たちが提供するサービスや商品の中にも、似たような構造があるのです。
現金のように「便利で自由度が高い」サービスを目指すだけでなく、ときに「用途を限定した設計」や「感情に訴える要素(パーソナライズ、ストーリー性)」を盛り込むことが、結果的にリピートや紹介につながることもあるでしょう。
つまり、「これは便利ですよ」と言うだけでなく、「このサービスを使って、どんな気持ちになってもらいたいか」までを考えること。そうした“届け方の設計”こそが、顧客との信頼関係や、印象に残る体験の原点になるのではないかと思うのです。
嬉しい記憶を「つくる」
同じ価値であっても、人の心に残るかどうかは、設計次第で大きく変わります。
さらに、社会や経済が複雑化し、多様な価値観が交錯する現代では、「何を提供するか」だけでなく、「どう届けるか」「どんな感情を引き起こすのか」にも目を向けたいものです。
たとえ同じ金銭的価値であっても、人の心に届くかどうかは、設計次第で大きく変わる。よしんばそれが現金であっても、そこに“意味”や“気持ち”が添えられていれば、きっとそれは、ただの数字以上の価値を持つはずです。
そのことを、今回の現金給付の報道を通じて改めて考えさせられました。
贈り手が“意味を込めて選んだもの”は、受け手にとっても“意味のある贈り物”になるのです。
💡コラム:人の心に残る“価値”をつくる4つの視点(キーワード)
- メンタルアカウンティング(心の会計)
現金=理性、贈り物=感情。用途が限定されているからこそ、感情が動くこともある。 - 贈与価値と記憶価値
人は「何をもらったか」ではなく、「どう感じたか」「どんな体験をしたか」を覚えている。 - 制限された選択の幸福
選べる範囲が狭いからこそ、「これを楽しもう」と素直に喜べることがある。 - シグナリング(気持ちの可視化)
現金よりも、“私のために選んでくれた”という意図が伝わるモノの方が心に響く。